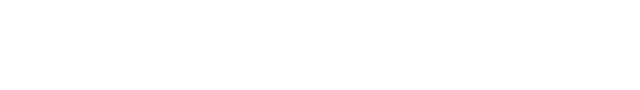歯周内科
当院は歯周病原因菌遺伝子診断認定歯科医院であり、歯周病の治療を専門としています。
院長は国際歯周病内科学研究会の認定医です。
歯周病の基本的な治療は、歯磨きや歯石除去などの歯のクリーニングです。
しかし、基本的な治療をしても、歯肉の炎症が解消せず、出血、排膿、口臭で悩んでいる方が見受けられます。
最新の医学では、虫歯や歯周病は風邪と同じく感染症であることがわかっており、原因となる菌の研究が進んでいます。
当院は、お薬により歯周病の原因となる菌を消滅させる内科的治療に力を入れています。
※歯周病の治療に関するお問い合わせは、お電話での回答が難しいため、当院にお越しいただきますようお願い申し上げます。
患者さまが普通に歯磨きをすれば、歯周病にならない、歯周病が治るという生活を求めて、歯周病の治療に科学的な診断、検査を導入し、歯周病治療の世界標準化を目指している研究会です。
歯周病の原因
歯周病の原因は細菌感染であり、歯周病は感染症です。
歯の表面に付着するプラーク(歯垢)の中には、300~400種、合計1億個以上の細菌が存在するといわれています。
また、お口の中にはカンジタ菌というカビの一種がいます。
カンジタ菌は虫歯や歯周病の原因菌と結びつきやすいため、カンジタ菌を減らすことが虫歯や歯周病の原因菌の減少につながると考えられています。
これらの細菌はバイオフィルムというバイ菌の巣を形成して住み着きます。
バイオフィルム中の細菌が血液の中に入ってしまう病気を歯原性菌血症といいます。
最新の研究では、歯原性菌血症は糖尿病やアルツハイマー病、心臓病、早産など、様々な病気や症状を引き起こすリスクとなることがわかってきました。
また、バイオフィルム中の細菌は人から人、人から動物へと感染します。
生まれたばかりの赤ちゃんは歯周病病原菌を保有していません。
乳児期や幼少期に親の持つ病原菌に感染して、歯周病病原菌を保有するようになります。
そのため、夫婦や親子揃っての歯周病治療をお勧めします。
歯周病の内科治療
まず、歯科医師によるカウンセリングを行ったうえで、位相差顕微鏡やリアルタイムPCR法を用いて患者さまのお口の中の病原菌の状態を観察します。
そして、歯周病の病原菌の種類や数を把握し、効果的なお薬を処方して治療します。痛みはありませんので、ご安心ください。
治療の流れ
歯周病の診査診断
歯科医師がお口の中をチェックし、歯周病の診断をします。
カウンセリング
1時間程度お時間をいただく、歯科医師によるカウンセリングを行います。
※カウンセリング料を頂戴しています。
位相差顕微鏡による菌の観察
顕微鏡でお口の中の菌の状態を確認します。
リアルタイムPCR法によるDNA検査
位相差顕微鏡で検査し、本格的に歯周病の内科的治療を進めることになった患者さまには、リアルタイムPCR法という精密検査を受けていただきます。
細菌を除去するお薬の内服
検査で判明した歯周病の病原菌の除去に有効な抗生剤や抗菌剤を処方させていただきます。
ご自宅にて内服ください。
カンジタ菌を除去するお薬の内服、もしくは、カンジタ菌を除去する歯磨き粉での歯磨き
カンジタ菌を除去する抗菌剤を処方させていただくか、専用の薬用歯磨きでのホームケアを指導させていただきます。
歯のクリーニング
歯石除去などのクリーニングを行います。
歯周病の改善
患者さまに治療前後の画像やデータを比較いただき、改善度合いをご確認いただきます。
位相差顕微鏡
お口の中の歯周病病原菌を生きたままの状態で顕微鏡の画面に映し出すことができます。
これを動画管理システムに記録し、原因となっている細菌を特定し、菌の数を把握します。
治療前後の写真、映像が比較できるため、患者さまには目視で改善度合いを確認いただけます。
リアルタイムPCR法
リアルタイムPCR法とは、歯周病の原因菌を特定する精密検査のようなものです。
位相差顕微鏡よりも菌の種類、数が詳細にわかります。
データは患者さまにお渡しさせていただきますので、治療完了後に再度行うリアルタイムPCR法検査にて菌の減り具合をご確認いただけます。
治療の効果
歯周病の内科治療では下記の効果が期待できます。
- 口臭がなくなる
- 歯磨きのときの出血がなくなる
- 歯がツルツルになる
- 歯肉がピンク色になる
- お口の中のネバネバ感が消える
- 歯の付け根がしみる感じが消える
その他の歯周病治療
下記の治療法は歯周病治療に非常に有効ですが、お口の中の状態によっては難しいことがあります。
スケーリング
軽度の歯周病の場合に行います。
スケーリングとは、歯肉より上についたプラーク(歯垢)や歯石、その他の沈着物をスケーラーという器具で取り除く治療です。
ルートプレーニング
中度の歯周病の場合に行います。
歯周ポケット内の歯石と病的セメント質を除去し、新たな付着を目的とするために行います。
歯と歯茎の境目の奥まで器具を入れ、痛みを伴うことがあるため、麻酔を併用します。
口臭測定
当院では、オーラルクロマという器械で口臭測定をしています。
治療の前後で口臭測定を行うことで、治療の効果をさらに実感いただけます。
オーラルクロマ
口臭の原因である三要素ガス(硫化水素、メチルメルカプタン、ジメチルサルファイド)の濃度を測定し、数値で把握する測定器です。